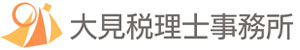今回も東京都世田谷区自由が丘にある大見税理士事務所から仮想通貨の解説をしていきます。今回は仮想通貨で税金が発生する可能性がある取引を見ていきます。ICOに参加したとき、仮想通貨FXをしたとき、アービトラージをしたとき、マイニングやエアドロップ、ハードフォークしたときなどを具体的に解説します。また具体的な計算の方法をわかりやすく記載しています。
今回も東京都世田谷区自由が丘にある大見税理士事務所から仮想通貨の解説をしていきます。今回は仮想通貨で税金が発生する可能性がある取引を見ていきます。ICOに参加したとき、仮想通貨FXをしたとき、アービトラージをしたとき、マイニングやエアドロップ、ハードフォークしたときなどを具体的に解説します。また具体的な計算の方法をわかりやすく記載しています。
仮想通貨で税金が発生するケース
取引所で売買する
投資目的で保有する仮想通貨を取引所で売却して得た利益は課税所得となります。所得税法上は原則的に雑所得に分類されます。この場合の売却損益の計算は、「売却価格-取得価格」で計算します。取得価格には取得にかかった手数料などの経費も含みます。
仮想通貨を別の仮想通貨に交換する
仮想通貨を他の仮想通貨に交換した場合、仮想通貨を売却して、新たに仮想通貨を得た、という複合取引になります。
売却と購入をしていますので、売却時に利益が出れば税金がかかります。売却損益の計算は「新たに取得する仮想通貨の購入価格-交換(売却)する仮想通貨の取得価格」で計算します。取得価格には取得にかかった手数料などの経費も含みます。
ICOで買って取引所で売る
ICOでトークンを買い、そのトークンが上場した後、取引所で売った場合も課税の対象となります。ICOの取得価格について、仮想通貨の交換と同じ様に考えるとわかりやすいでしょう。
取得した時点でのICOトークンはまだ上場しておらず価格がついていないため、時価がない0円のトークンを時価があるビットコインやイーサリアムで交換をすることになります。ビットコインなどは0円のものと交換になるのでビットコインでは0円の収入、費やした数量分のビットコインは必要経費になり、結果としてビットコインの計算では損になります。トークンは取得した時は価値が0円だったため必要経費は0円、上場後売却するとその金額がそのまま雑所得になります。上場後に売却した場合、ICOトークンの時価が利益となります。またはICOトークンの時価は0といっても参加する際に価格はついているため、その価格で売却したと捉え、同時にその価格でICOトークンを購入したと考えます。
ICO参加時の所得計算に関しては、別の考え方もあります。対価として支払った仮想通貨の時価をICOトークンに出資したと考える方法などです。
どの考え方でも結果的に売却時の利益は同じになります。しかしICOに価格がつかなかったり、廃止されたりした場合の損失計上の煩雑さを考えると、取得時の価格はゼロにしておいたほうが計算は楽でしょう。
明確に決まった方法はありませんが、毎回同じ処理方法を取ることが重要です。取引によって使い分けをすると、客観的に見て正当な処理と認められにくくなるからです。
仮想通貨取引所のFXで取引する
仮想通貨取引所のFXで取引をした場合、実際に取引の損益が確定した時点で所得が発生します。ポジションを持っている(含み損や含み益が発生しているが決済はしていない状態)だけでは、収支は発生していませんので、税金もかかりません。仮想通貨の証拠金取引はビットコインFXと呼ばれていますが、他のFXとは利益通算できないので注意しましょう。
お店で決済に使った時点で利確
仮想通貨を商品やサービスの対価として支払った場合、税法上はその時点で仮想通貨を譲渡したと考えます。つまり支払った時点で利確となり、損益が発生します。
アービトラージで収益を得る
アービトラージとは、裁定取引(さいていとりひき)といって、同一価値のものの価格差を利用した取引のことです。仮想通貨取引のアービトラージは、取引所ごとの価格差を利用して利益を得ようとする方法をいいます。売却した時点で利益が確定するのは、他の取引と同じです。
マイニング、エアドロップ、ハードフォークなど
マイニングの場合、取得した仮想通貨の時価からマイニングにかかった費用を引いた金額が所得金額になります。
エアドロップはもらった時点の時価を所得金額にします。もらった時の時価が1,000円なら利益が1,000円です。価値が2,000円になった時点で売却すると、さらに1,000円の利益。合計2,000円の利益という計算です。
ハードフォークによる仮想通貨の取得は、所得金額0円と考えます。ハードフォーク(分岐)した時点では市場価値がないからです。
仮想通貨の税金、こんな時どうする?
1.取引所における日本円による売買
取引所における日本円での売買では、仮想通貨の売却価額と取得価額との差額が課税所得額となります。
取引内容
1月10日 1,000,000円で5BTCを購入した。
2月20日 2BTCを500,000円で売却した。
所得金額の計算
[売却価額]-[1BTCあたりの取得価額]×[支払ビットコイン]=[所得金額]
500,000円-(1,000,000円÷5BTC)×2BTC=100,000円
所得金額は10万円と計算されます。一年に一度しか購入をしていなければ、計算は非常に単純です。次に、複数回にわたり繰り返し購入した場合の計算方法をみていきましょう。
取引内容
1月10日 1,000,000円で5BTCを購入した。
2月10日 250,000円で1BTCを購入した。
3月10日 1,500,000円で5BTCを購入した。
4月20日 2BTCを800,000円で売却した。
12月10日 1,000,000円で1BTC を購入した。
所得金額の計算
移動平均法
移動平均法を用いた場合1BTCあたりの取得価額は購入の都度、変化します。
4月20日売却時点での取得価格の計算式は次の通りです。
(1,000,000円+250,000円+1,500,000円)÷(5BTC+1BTC+5BTC)=250,000円
250,000円を取得価格として所得金額を計算します。
[売却価額]-[1 BTCあたりの取得価額]×[支払ビットコイン]=[所得金額]
800,000円-250,000円×2BTC=300,000円
所得金額は30万円と計算されます。
総平均法
総平均法を用いた場合、1BTCあたりの取得価格は年間の平均取得価格を用います。
平均取得価格の計算式は次の通りです。
(1,000,000円+250,000円+1,500,000円+1,000,000円)÷(5BTC+1BTC+5BTC+1BTC)=312,500円
312,500円を取得価格として所得金額を計算します。
[売却価額]-[1 BTCあたりの取得価額]×[支払ビットコイン]=[所得金額]
800,000円-(312,500円×2BTC)=175,000円
所得金額は17万5千円です。
2.取引所における仮想通貨による売買
取引所における仮想通貨による仮想通貨の売買(交換)は、仮想通貨を売却して日本円を得て、その日本円で別の仮想通貨を購入したと考えます。
取引内容
1月10日 1,000,000円で5BTCを購入した。
10月20日 1BTCで10ETHを購入した。
10/20のレート
ビットコイン 500,000円/BTC
イーサリアム 50,000円/ETH
所得金額の計算
ビットコインを売却してイーサリアムを購入したと考えますから、交換時に所得を計算します。
[売却価額]-[1BTCあたりの取得価額]×[支払ビットコイン]=[所得金額]
500,000円-(1,000,000円÷5)×1BTC=300,000円
所得金額は30万円です。
3.ハードフォークで付与されたアルトコインを売った
ハードフォークで得たアルトコインは、取得時に時価がなかったと考えます。
取引内容
8月1日 BTCのハードフォークで2BCHを取得した。
11月1日 2BCHを100,000円で売却した。
11/1のレート
ビットコインキャッシュ50,000円/BCH
所得金額の計算
[売却価額]-[1 BCHあたりの取得価額]×[支払ビットコインキャッシュ]=[所得金額]
100,000円-0円×2BCH=100,000円
所得金額は10万円です。
4.エアドロップで取得した仮想通貨を売った
エアドロップで取得した仮想通貨は、もらった時点の時価を取得価格と考えます。
取引内容
2月1日 0.5 VIBを取得した。(レート30円/VID)
3月1日 1 VIBを取得した。(レート30円/VID)
4月1日 0.5 VIBを取得した。(レート30円/VID)
5月1日 3 VIBを取得した。(レート10円/VID)
6月1日 1 VIBを取得した。(レート30円/VID)
7月1日 1 VIB を取得した。(レート50円/VID)
8月1日 2 VIBを取得した。(レート60円/VID)
9月1日 1 VIBを取得した。(レート70円/VID)
10月1日 0.5 VIBを取得した。(レート80円/VID)
11月1日 0.5 VIBを取得した。(レート80円/VID)
12月31日 10VIDを1,000円で売却した。
12/31のVIDレート
レート100円/VIB
取得時の所得金額計算
2月1日 0.5 VIB×30円=15円
3月1日 1 VIB×30円=30円
4月1日 0.5 VIB×30円=15円
5月1日 3 VIB×10円=30円
6月1日 1 VIB×30円=30円
7月1日 1 VIB ×50円=50円
8月1日 2 VIB×60円=120円
9月1日 1 VIB×70円=70円
10月1日 0.5 VIB×80円=40円
11月1日 0.5 VIB×80円=40円
合計440円(11VIB)
所得金額の計算:総平均法を用いた場合
取得価格の計算式は次の通りです。
(15円+30円+15円+30円+30円+50円+120円+70円+40円+40円)÷(0.5 VIB+1 VIB+0.5 VIB+3 VIB+1 VIB+1 VIB+2VIB+1 VIB+0.5VIB+0.5VIB)=40円
40円を取得価格として所得金額を計算します。
[売却価額]-[1 VIBあたりの取得価額]×[支払ヴァイブレート]=[所得金額]
1,000円-40円×10VID=600円
所得金額は600円です。
5.お店で決済に使った
電気店や飲食店など、仮想通貨が使用できるお店で支払いに使うと、その時点での含み益が所得になります。
取引内容
2月20日 1,000,000円で5BTCを購入した。
3月20日 電気店でパソコンを1BTCで購入した。
3/20のレート
ビットコイン210,000円/BTC
所得金額の計算
1,000,000円で購入した5BTCのうち、1BTC(200,000円)を210,000円で売却したことになります。
[売却価額]-[1BTCあたりの取得価額]×[支払ビットコイン]=[所得金額]
210,000円-200,000円×1BTC=10,000円
所得金額は1万円です。
6.マイニングで手に入れた仮想通貨を売った
マイニングで取得した仮想通貨は、取得時の時価からマイニングにかかった費用を差し引いた額を利益とします。
取引内容
6月1日 マイニングで1BTCを取得した。(マイニングにかかった費用500,000円)
12月1日 1BTCを1,000,000円で売却した。
6/1のレート
ビットコイン600,0000円/BTC
取得時の所得金額計算
[時価]-[必要経費]=[所得金額]
600,000円-500,000円=100,000円
取得時の所得金額は10万円です。
売却時の所得金額計算
[売却価額]-[1BTCあたりの取得価額]×[支払ビットコイン]=[所得金額]
1,000,000円-600,000円×1BTC=400,000円
売却時の所得金額は40万円です。
7.アービトラージで取引しまくった場合
アービトラージ取引では、原則として取引時の時価を使って損益を計算します。
例えば次のような取引をした場合、所得は45,000円です。
| 取引日 | 1月1日 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 | 1月5日 | 1月6日 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入 | ¥200,000 | ¥190,000 | ¥180,000 | ¥200,000 | ¥200,000 | ¥300,000 | ¥1,270,000 |
| 売却 | ¥210,000 | ¥200,000 | ¥185,000 | ¥205,000 | ¥220,000 | ¥295,000 | ¥1,315,000 |
| 差損益 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥20,000 | ¥-5,000 | ¥45,000 |
すべて1BTC取引
アービトラージは取引数が多くなると、所得の計算が非常に煩雑になってしまいます。その場合、ソフト等を利用して計算を自動化することができます。ただし現状では、取引所がソフトに対応していないケースも多くあります。
どうしても取引時の時価で計算ができない場合は、例外的に仲値などの一定の取得価格を用います。取得価格を一定にすることで計算は簡便化できますが、算出された所得が実態と乖離してしまうといったデメリットもあります。
例外的な計算方法を用いる場合には、きちんと説明できる合理的な理由が必要です。この場合は「原則的な計算方法では、計算ができない」というのが合理的な理由です。
また、計算方法は必ず統一し、継続適用することも租税回避目的と疑われないための重要なポイントです。
8.仮想通貨に代えて日本円で補償を受けた場合
取引所がハッキングされて仮想通貨が盗難された場合、補償金を受け取った時点で仮想通貨を売却したと考えます。
取引内容
1月1日 800,000円で10,000XEMを購入した。
1月26日 利用していた取引所で盗難の被害が発生した。
3月12日 XEMに代えて日本円880,000円で補償を受けた。
1/26のレート
NEM100円/XEM
所得金額の計算
被害が発生した時点での時価は使用せず、実際に補償を受けた金額で売却したと考えます。
[売却価額]-[1 XEMあたりの取得価額]×[支払NEM]=[所得金額]
880,000円-80円×10,000 XEM=80,000円
所得金額は8万円です。
仮想通貨の確定申告で脱税等でニュースになってしまうととても大きなダメージを受けてしまいます。大見税理士事務所では仮想通貨の税務調査を積極的に受け付けております。コロナの影響で税務調査がしばらくおこなわれていませんでしたが2020年10月から順次再開するという報道がなされています。仮想通貨が高騰した2017年から3年経過しております。もしも無申告だったり不正をしているかたがいらっしゃったら税務調査前であればリカバリーはできます。ぜひとも大見税理士事務所へご相談ください。