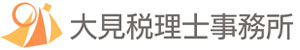被相続人が亡くなり、その年(1月1日から亡くなった日まで)に一定の所得があった場合、相続人は被相続人の代わりに確定申告をして、所得税を納めなければなりません。これを準確定申告といいます。
被相続人が亡くなり、その年(1月1日から亡くなった日まで)に一定の所得があった場合、相続人は被相続人の代わりに確定申告をして、所得税を納めなければなりません。これを準確定申告といいます。
準確定申告・・・相続開始を知った日の翌日から4か月以内に行う(期限を過ぎると延滞税などがかかる)
注意!通常の確定申告と同じ期限ではない(翌年の3/15)ので気をつけましょう
自営業などの人はもちろん、収入が給与・年金だけだった人でも、医療費が多かった場合には、医療費控除などの適用により、確定申告をすることで、還付を受けられる可能性があります。
納めた税金は、相続財産から差し引くことができ、還付金は相続財産の一部となります。
確認! 所得税の税率(速算表)
- 課税所得金額
- 税率
- 控除額
- ~195万円
- 5%
- なし
- 195万円~330万円
- 10%
- 9万7500円
- 330万円~695万円
- 20%
- 42万7500円
- 695万円~900万円
- 23%
- 63万6000円
- 900万円~1800万円
- 33%
- 153万6000円
- 1800万円~4000万円
- 40%
- 279万6000円
- 4000万円~
- 45%
- 479万6000円
- Point
- 消費税の課税事業者で、被相続人が事業を行っていた場合、併せて消費税の申告も必要になる。
前年の申告書の控えなどをよく調べ、必要な申告内容を確認しましょう。
- 純確定申告が必要になるケース
-
- 個人事業を行っていた
- 株式や不動産などの売却収入があった
- 2000万円を超える給与収入があった
- 年の途中で退職して年末調整を受けていない
- メインの給与所得以外に20万円を超える所得があった
- 医療費控除などにより還付金を受けられる
- アパートなどの賃貸収入があった
など
- 確定申告
- 確定申告とは、その年の所得をとりまとめ、所得税を自ら計算して納めることです。個人事業主など以外でも、株や不動産の売買などで利益を得た場合には、確定申告が必要です。毎月の源泉徴収と年末調整で納税が完了しているサラリーマンは、確定申告は原則不要です。ただし、年収が2000万円超、給与以外に20万円超の所得がある人などは、申告が必要です。
困ったとき・わからないときは・・
専門家に相談しましょう!!
★税金のこと→税理士に相談してください
相続税では、現金、株式、不動産など多岐にわたる相続財産の評価、分割方法、相続人や受贈者間の調整など、数多くのことを考慮する必要があります。金額も大きいため、ミスは許されません。不安や心配、また「手に負えない」と感じたら、早めに専門家の手を借りるようにしましょう。
相続税のことであれば、税理士に相談するのが一般的です。生前から相続税がかかることがわかっている場合は、早めに税理士に相談することで、無駄な税金を払わないことができます。
また、法律にかかわる問題(例えば、遺産分割の争いなど)がある場合、弁護士に相談しましょう。当事務所では弁護士先生とも連携をしておりますのでスムーズに対応できます。