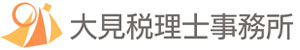相続税申告のための資料収集しよう
相続税申告のための資料収集しよう
1.戸籍をとろう
まずやらなければいけないことは、亡くなった人と相続をする人の戸籍謄本の取得がまず第一になります。
特に亡くなった方については生まれた時から死亡した時までの戸籍が全てつながって初めて相続人の確定ができることになります。
ただし、相続税の申告をしなければいけない人というのは法定相続人だけではなくて贈与を受けたものなども含まれますので戸籍だけでは十分ではありませんので注意です。
もし亡くなった方の本籍地が分からなければ、住所地の住民票を取れば本籍地が記載されています。
住居を転々としている場合は、最後の戸籍から順番にその前の戸籍を追うことで出生時から死亡時までの戸籍を繋げなければいけません。
もし相続人に未成年者の方がいる場合は通常親が代理人なることがほとんどだと思います。しかし、相続に限っては親も子供と利害関係にあることがあるので、利益相反と言って親権を行使することができないことがあります。
そういった場合は第三者を立てる必要があるので家庭裁判所などに申立をしたり、叔父や叔母などへ相続人以外で信用できる方に依頼したりすることも考えましょう。
2.預貯金からまとめよう
次に行うべきことは、亡くなった方の預貯金や有価証券等についてまずは分かる範囲内でまとめましょう。
銀行ごと、支店ごとに相続開始した日の残高証明書や通帳の取り寄せから始めましょう
過去の通帳が残っていない場合は銀行に依頼をすれば口座ごとに入出金の状況を復元しなければいけません。残高だけではなくて履歴も必要になります。
銀行の取引履歴を分析していくと例えば配当金があれば株をやっていたとか何か資産を購入したり売却したりそういった事実が明らかになるからです。
通帳を手に入れたらまずは多額の入出金をチェックしましょう。
例えば入金からは何かしら資産が売却されたことが考えられるので最終的なその資金の行方というものも確認する必要があります。
資産を買っていればそのもの、また、何かサービスを受けたというものであればその内容もチェックし、何も使っておらず現金預金のままということであればそれはそのまま残高に反映されるはずです。
税務署は相続税の申告書が提出されると記載されている金融機関に対して過去の預金の入出金の状況を照会することができます。
納税者が過去の通帳を出そうが出すまいが預金の移動状況というのは既に把握済みであるということですので隠すことはおすすめしません。
また定期的な引き落としからも例えば保険の加入状況や借金の有無など特定することもできます。
貸金庫の引き落としがされていれば、貸金庫の中の中身というものも税務署にとっては確認したい所になりますよね。
名義預金は必ず調査で聞かれる
相続税の調査の中で必ず聞かれる事柄が名義預金や名義株という問題です。
これは親心でもあるんですが子供のために子の名義で預金通帳を作りその通帳に親が子の名義でお金を積み立てたり貯金をしていくものを言います。
これは名義としては子供のものですが支配をしているのは親になりますので、親の財産として計上しなければいけません。もし子供が使っているということであれば贈与になりますので贈与税の申告もれということにもなりかねません。
名義預金というのは必ずチェックをされる項目ですのでこの点については慎重に確認しましょう。
他にも例えば、亡くなった方が仕事をしていた場合で、配偶者の方が無職だった場合つまり専業主婦とかですね。この場合は亡くなった方より配偶者の方の方が貯金が多かったりすると通常ありえない状況ですよね。こういった場合は例えば贈与だったり名義預金だったりするというところで調査の対象にもなりかねません。
3.不動産の資料あつめ
不動産についてはかなり準備が必要になります。固定資産の名寄帳に従って、全ての不動産をもれなく把握することから始めましょう。特に道路の幅や接している状況、計画道路の有無、埋蔵文化財など色々な出来事が影響を与えることになります。
毎年通知がくる固定資産税の納税通知書もチェックをしましょう。
地番というものが通知書に表示をされていますので、それに基づいて登記簿謄本を取得したり、公図や地積測量図などを取り寄せましょう。
また、名寄帳というものがありますがこれは、所有者ごとに土地建物を帳簿に記載してそれをもとに納税通知書を発送しているものです。不動産によっては非課税のものもあり固定資産税の納税通知書だけではわからないこともありますので該当しそうな方はチェックすることも必要になるでしょう。
また私道の存在があります。
相続税法の中では評価額がゼロにならない私道の存在もあるので注意をしましょう。私道がある場合、財産の計上がもれていることになると遺産分割の対象から外れてしまい相続登記が未了の土地が発生することになります。
その他、住宅地図や路線価図が必要になります。住宅地図は図書館や地域によってはインターネットで取り寄せることもできます。路線価は国税庁のホームページから無料で入手することができます。また自宅や近くの場所であれば問題ないのですが遠方に土地がある場合は現地調査などの作業も発生します 。
土地の形状がいびつだったり急な斜面があったりすると価値が下がるので相続税の負担が下がる可能性があります。
そういったものは実際に現地をみてみないとわからないこともあるのでチェックしてみましょう。