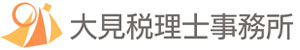円満な財産の分割を考える場合は遺言書の他に効果的な方法はありません。
円満な財産の分割を考える場合は遺言書の他に効果的な方法はありません。
亡くなった方が遺言を残していた場合、自分の考えが財産の分割に反映されて、残された人たちの無駄な争いというものは避けることができるからです。税理士としては「争続問題を回避するために必ず残しておくべきです。」とお伝えをしております。
円満な相続が行われることもあります。
しかし多かれ少なかれ人間には損得勘定があるので、もし相続財産の不満があればそれがきっかけとなって爆発することがあります。
遺言書のなかになくなった方がなぜこのような分割をしたか思いを伝えることで完全に公平な分割ではなかったとしても納得がしやすいからです。
逆に故人の意思がない分割は仲が良い家族ならともかく前妻の子など利害関係がない人からすると不満がでます。
それを回避する方法はいろいろありますが、基本的に遺言書の作成というものが一番の争続回避に有効な手段といわれています。
また相続税を計算するときに誰がどの土地を相続するかによって相続税の軽減ができたり、できなかったりするので税理士が遺言書の作成に関与することは残された人達にとって有利になります。
- 遺言書は3種類
-
遺言書には 自分で書く自筆証書遺言というものと、交渉人で書いてもらう公正証書遺言というものがあります。
その他に秘密証書遺言というものがありますが基本的にはあまり使われない制度になっています。
自筆証書遺言というのは書かなければいけない形式が決まっていて、万が一の場合は遺言が無効になる可能性があるのが怖いところです。
それを避けるために公正証書遺言というものをお勧めしています
- 事前の準備
-
公正証書という言葉から、ちょっと敷居が高いように感じられますが税理士がお手伝いをする場合は遺言をする人に代わって公証人役場に必要書類を添えて提出しておけば大丈夫です。
交渉人がそれを元に文章を書いてくれますので、その後に文面をチェックして確認するだけなのでむしろ簡単です。
自分で書く自筆証書遺言は若い方ならともかく、高齢の方が一人で書いても無効になる可能性がありおすすめしません。
開封する際も一定の手続きが必要になるので手間もそこまでかわりません。
- 公証役場へ
-
事前の準備ができたら遺言者本人と一緒に決められた日時に公証人役場に行くことになります。高齢で動けない場合は来てもらうこともできます。
そこでは公証人が事前に準備した書類を読み聞かせることによってそれが間違いないことを確認して署名押印することになっています。
公証人は法律のプロですのでそこで形式が不備だったりすることはまずありません。
また遺言者にとっても信用できる税理士がいることで安心感があります
- 争いになる可能性を少しでも低くするため
-
遺言書を作成する最大の目的それは財産の分割で相続人の争いを避けることです