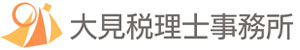相続には、生前の贈与や財産への貢献度も影響する
- 相続人の中に、生前、結婚支度金や留学費用・ローンの頭金等をもらっている人 特別受益
- また、被相続人の生活の世話をしたり、家業を無償で手伝ったり、事業資金を提供したなど、財産の維持・増加に貢献したと考えられる相続人がいる場合 寄与分
*相続では、公平な分割が行われるよう、これらの金額を考慮することになっています。
- 特別受益を受けた相続人の相続分が減り、寄与分のある相続人の相続分は多くなります。
特別受益は、相続財産の一部として計算します。
- 特別受益となるのは、
-
- 相続人に対する
-
- 婚姻や養子縁組のための贈与
- 生計の資本としての贈与(主に住宅取得資金や事業資金など)
*通常の生活資金や学費などは、原則含まれません
1,2とも金額や内容により、遺産分割協議で相続人が個別に判断します。
他に、遺贈も特別受益です。
◎特別受益のある人は、その分を相続財産から差し引きます
1、相続人に特別受益のある人
(特別受益者)がいる
A
B
C特別受益者
- Point
- 特別受益者となるのは
- 相続人に遺贈された財産
- 生前贈与された一定の財産
(結婚の際の支度金、住宅資金や独立開業資金など)など
2、特別受益分を相続財産に加える(持ち戻し)
- 相続開始の財産
- 特別受益分
3、2の金額をそれぞれの相続割合で分ける
- A
- B
- C特別受益者
4、特別受益者の相続分から、特別受益分を差し引く
C特別受益者
これが特別受益者の相続分となる。計算の結果がゼロやマイナスになった場合、相続財産は受け取れない。
寄与分があれば、その相続人の相続分が多くなる
1、相続人に寄与分のある人がいる
A
B
C寄与分がある
- Point
- 寄与分となるのは
- 家業などの被相続人の事業を、ほとんど無給で手伝っていた人
- 債務を肩代わりしたり、被相続人の事業などに資金を提供した人
- 被相続人の療養介護などを、献身的に行っていた など
2、寄与分をお金に評価して、相続財産から差し引く
- 相続財産
- 寄与分
3、2の金額をそれぞれの相続割合で分ける
- A
- B
- C
4、寄与分のある人の相続分に、寄与分を加える
C
これが寄与分のある人の相続分