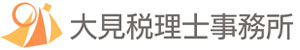相続税がかかる財産はお金に変えることができるものすべてと考えてください。最近では仮想通貨も相続財産に含まれると規定されました。骨董品や特許権などの形がないものもお金に変えることができるので財産に含まれます。
相続税がかかる財産はお金に変えることができるものすべてと考えてください。最近では仮想通貨も相続財産に含まれると規定されました。骨董品や特許権などの形がないものもお金に変えることができるので財産に含まれます。
相続税には、プラスの財産と負の財産があります。
- プラスの財産
- 預貯金・株式・有価証券・不動産・車・家財・書画・骨董品
特許権や著作権などの無形の権利(お金に換算できるのであれば課税対象になる) - 負の財産
- 借金・未払金など被相続人の債務
相続税の計算では、プラスの財産-負の財産差し引くことができる
墓地や仏壇など金銭的な価値があっても、相続税がかからない財産⇒非課税財産
相続税の対象となる財産
- 相続財産(プラスの財産)
-
- *現金、預貯金
- *不動産;住んでいる家(自用家屋)とその土地、賃家と賃宅地、店舗、田畑、山林など
- *有価証券:株式、公社債、投資信託など
- *債権:貸付金、売掛金など
- *家庭用財産:車、家具、貴金属、宝石、書画・骨董品など
- *その他:ゴルフ会員権、特許権、著作権、電話加入権など
原則として
金銭に換算できるものは
全て相続財産
金銭に換算できるものは
全て相続財産
- 負の財産
-
- *借金(ローンやカードの未決済分など)
- *未払金(医療費や税金など)
- *預り金(敷金など)
要注意
被相続人の借金は
財産の一部
被相続人の借金は
財産の一部
- 相続財産とされるもの(みなし相続財産)
-
- *生命保険金(生命保険契約の権利を含む)
- *個人年金など定期金に関する権利
- *死亡退職金
被相続人自身が残したものではないが相続財産に含む
- 非課税財産
-
- *墓地・墓石、仏壇・仏具、神棚・神具などの費用
- *生命保険金などの一定部分(非課税枠=法定相続人の数×500万円)
- *死亡退職金などの一定部分(非課税枠=法定相続人の数×500万円)
- *国や地方公共団体、特定の公益法人などに寄付した財産
被相続人の葬儀で受け取った香典や花輪代等は、相続財産に含まれません。葬儀にかかった費用(香典返しを除く)は、相続財産から差し引くことができます。
- 要注意!
- 相続開始後、被相続人の預貯金口座は凍結され、勝手に引き出すことはできなくなりますので、葬儀費用や当座の生活資金などは、相続人が協力して立て替えておき、分割終了後に相続財産により精算となるため、前もって、分担など相続人の間で話し合い、決めておきましょう。